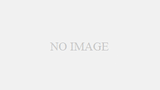初節句で兜を買わない選択ってありなのでしょうか?
置く場所なども限られています。
代わりとしてのお祝いなどはどういったものになるのでしょう?
いろいろ気になります。調べてみました。
初節句で兜を買わない人ってどのぐらいいるの?理由は?
端午の節句で五月人形を飾る家庭ってどのぐらいいるのでしょうか?
あなたのご家庭では、今年の端午の節句の時期に五月人形を飾りますか?
※単一回答 / 18歳までの男のお子さまがいる方(n=1000)
飾る(44.9%)
持っているが飾らない(16.8%)
飾らない(38.3%)
出典元http://lifemedia.jp/everyen/entries/74
五月人形を飾らない(買っていない)という家庭が4割近くをしめています。
意外にありますね。
買わない理由としては
①住宅環境により飾る場所がない。
②収納場所に困る。
③五月人形を飾る意味がわからない。
という感じです。
昨今では住宅事情で場所を取ってしまう五月人形は
飾れないといった意見は特に多くあるようです。
初節句で兜を買わない場合はどのように祝ったらいいの?
住宅事情などで、五月人形や兜は買わないという選択を
していく場合などは、事前に両家のご両親には、
事情をお話しして了解を取っておくようにしましょう。
よく話し合っておかれることで、
当日はご両家の両親も一緒に別の形で気持ちよくお子様のお祝いをしてあげる工夫ができます。
時代が流れても兜を飾るといったことは
当時の男子に与えられた強い宿命を感じとることもできます。
今の時代において子供へ対しての思いは
昔も今も共通の部分もあり、
大切な子供の厄除けをし、立派に成長させていく
といった願いも込められています。
何か形を変えたお祝いの仕方など考えてみましょう。
手作りの初節句で兜作り
①兜を画用紙などで手作り
②鯉のぼりの布のタペストリー
③色紙で兜やこいのぼりを作ってみる
④玄関に菖蒲の花を飾る
両家のお父様やお母さまなども一緒に、
1年に一度の行事である端午の節句では、
柏餅を食べたり、お寿司を食べたりして
一緒にお祝いをしてあげるといいですね。
お子様にとって記念に残るイベントにしてあげることができます。
初節句、端午の節句の由来は・・・
■初節句の由来は・・
日本の行事である端午の節句には、
古来より伝え続けられてきた大切な想いがあります。
そもそも端午の言葉の端は月の始まりのことをいいます。
そして初節句が5月になった理由も
午の読み方がそのまま五に通じたともいわれています。
5月は稲を実らせるための最初の種まきの月ともなります。
稲の神様には豊穣を願うといった風習は古来よりありました。
■端午の節句の由来は・・
古くより邪気ばらいとして菖蒲の花やよもぎを
玄関に飾ることを厄災としており、
そのまま端午の節句と結びついていったようです。
理由としては菖蒲と尚武が同じ読み方である
といったことがあげられます。
江戸時代の武士の間では縁起がいいことである
といわれるようになりました。
江戸時代にはそういった経緯もあり、
一気に端午の節句は正式な行事として幕府にも認められ、
徐々に庶民にも広がりを見せていきました。
日本独特の漢字の読み方が古来より端午の節句の行事の
発祥にもつながっていったのです。
■兜の由来は・・
①縁起ものである点
②邪気を払うという習わし
③強くたくましさを願う風習、
など兜へ対しての想いは、大切にしていきたい日本の行事である端午の節句としてこれからもその伝統は伝えていきたいことでもあります。
実際に孫の為に五月人形の買うのは、
母親または父親のご両親となる場合が一般的です。
地方によりどちらの実家が買うのかは異なりますが、
男の子が生まれたら購入することが当たり前のようになっているのが、
昨今の日本の風習の一つともいえるでしょう。
初節句には、当然のようにどちらかの親が購入して
孫に贈るといったことが多くあるようです。
まとめ
初節句だけど、兜を与えられた環境の中では
買わない選択をしていくこともあるでしょう。
ですが、大切に伝えられてきた端午の節句にこめられた
日本古来からの想いを知ることで、
改めて子供の成長に対して様々な願いを持つこともできます。
頼もしく成長していく子供の姿に対して、
形式にとらわれないあなたらしいお祝いの形を
作ってあげることもお子様にとっては大切な記念の1ページとなります。